新作書籍「海外旅行は自分を変える最強の武器」発売!
コロナ禍前から執筆を進めていた新刊書籍ですが、コロナ禍を経て内容を大幅に加筆修正して遂に発売になっています!
海外旅行は自分を変える最強の武器
本書は、年内はAMAZON Kindle での発売、年明け以降徐々に他の電子書籍プラットフォーム、更には2022年春以降は紙の書籍としても発売されるとのことです。
私が過去に出会った「国内外のエグゼクティブたち」彼らの旅に対する姿勢は衝撃的でした。
「旅で得たヒントを仕事や生活に活かしたい」と考えている私に大いにヒントを与えてくれました。
今回はそんな彼らエグゼクティブたちの「旅ライフ」を紹介します。是非チェックしてみてください。
<本書の紹介>
外資系エグゼクティブたちが実践している旅の秘訣とは?
仕事に活かせることも、人生を楽しく生きることも、実は「海外旅行」からさまざまなヒントが得られます。そのことを理解している海外の「外資系エグゼクティブ」たちは、成長を続けています。
新型コロナウイルスの影響から徐々に世界が立ち直り、旅・旅行が再開されつつある今、「旅ライフ」の構築により、ビジネスパーソンとして成長するヒントをお届けします。
外資系エグゼクティブたちが、なぜ旅を重視して自身の生活の一部として取り入れているのか、何を意識して行動しているのか。その答えの中には、情報収集・時間管理・スキルアップなどの具体的方法、人脈の広げ方、仕事のマネジメント、家族の在り方まで、成功者のマインドセットを得る方法などが見えます。日本人・ビジネスパーソンであるあなた自身にも取り入れられることが多いでしょう。
年間30か国をビジネスで巡るビジネストラベラーの著者が、旅や仕事で出会ってきた世界中のエグゼクティブたちの驚きの行動や考え方を徹底解明する1冊!
本書を読むことで、次の旅や海外旅行が劇的に変わるでしょう。
【目次】
第1章 外資系エグゼクティブに学ぶ 旅で人生を変える方法
第2章 外資系エグゼクティブの旅ライフ
第3章 外資系エグゼクティブがもつ旅のマインドセット
第4章 外資系エグゼクティブが実践している旅先での驚きの行動
第5章 あなたにもできる「旅を取り入れて成長を加速させるライフスタイル」のつくり方
上記はあくまで2021年8月時点での予測であり、日本から日本人が海外渡航することを前提としてます。また海外渡航にはまだまだハードルが高く、コロナ前のようき気軽にいけない事情があります。
今後の海外渡航のチェックしておくべき点については、拙著「コロナ禍での海外渡航術」をご覧ください。
読者キャンペーン
今月いっぱい「AMAZONレビュー」キャンペーンで購入者特典をご用意しています。
【購入者特典】
特典①バーチャルツアー「知られざる次の観光大国~サウジアラビアの旅」ご招待
特典②「コロナ禍の海外渡航術」特別版 ~コロナ禍で海外に行くということとは!~
特典③あなたも今すぐ海外に行ける! アフターコロナの旅のチェックリスト!
2021年10月1日からどう変わる!?海外からの帰国!
海外から帰国した際の政府指定のホテル「強制隔離」って実際どうなの!?
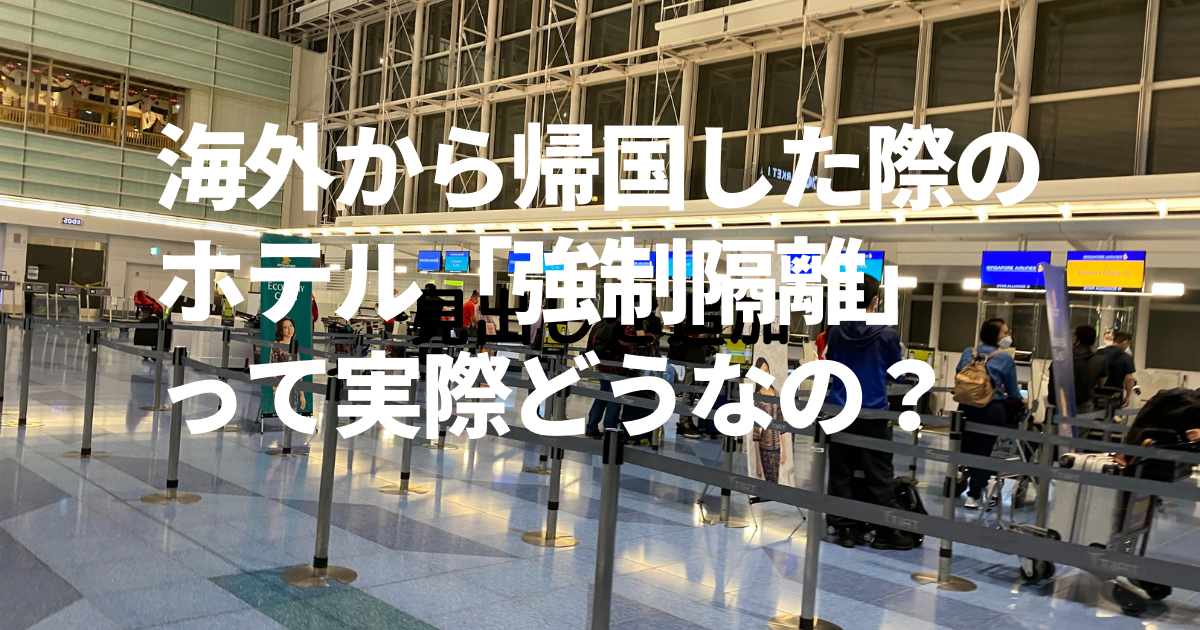
海外から帰国したら政府指定のホテルに「強制隔離」されるってホントですか?
よくいただく質問…答えは「そのとおりです」
そうなんです、渡航先により帰国してから、最長10日間、政府指定のホテルにカンヅメ状態で部屋から一歩も出られません。私も2021年体験しました。
拙著「コロナ禍での海外渡航術」を発売した2021年1月時点ではなかった制度であり、公式ブログにてアップデートの意味を込めて解説、および私自身の体験をシェアさせて頂きたいと思います(↓リンク先)
- 政府指定のホテルに強制隔離?「検疫指定隔離」とはどんな制度?
- 部屋から一歩も出られない!? 隔離期間のリアル
- 今後隔離期間を意識しての海外渡航計画について気を付けること
-声のブログ:Stand.FM「バミューダチャンネル」
Twitterもチェック!
海外旅行にいつから行ける?旅のプロの見解は?(Part.2)
海外旅行にいつから行ける?旅のプロの見解は?
アップデート~緊急事態宣言解除が視野に「国内旅行が動き出してきている」
さてブログのリニューアルと共にこちらの Hatena Blog の更新は原則ありませんが、最近の更新状況をお知らせします。実は結構活発に活動しております(笑)
コロナウイルス感染拡大状況は未だ予断を許さず、首都圏中心に緊急事態宣言解除にも慎重な姿勢がうかがえます。一方で徐々に地方から国内旅行が再開されつつあります。感染対策と経済回復のバランスを取っていかなければいけませんが、旅が好きな人・旅から得られる貴重な成長や学びの機会を重視されている人「旅の準備」はそろそろ始める時期にきているのかもしれません。
情報発信を音声メディアに切り替えてつつある中で最近の「旅のアップデート」配信をいくつかご紹介させて頂きます。宜しければ是非お聴きください。
【お得に旅するヒント】オーバーツーリズムからのマイクロツーリズム
【旅のフットワーク】思い立ってすぐ行動 今から今夜の便で海外行けますか?
【タダでホテルに泊まれちゃう⁉︎】お得な旅の予約の探し方〜急げ〜
【続 タダでホテルに泊まる方法】ご連絡いただきありがとうございました〜
Googleがみている!アフターコロナの旅の準備
【GoToイベント】覚えてますか?静かに再開中!
<情報発信更新状況>
1.ブログサイトを別途リニューアル
2.日々の情報発信をブログから音声メディアに切替え
音声メディアについてはその可能性については別途解説させて頂きたいと思いますが、ポッドキャスト系メディア(私の活動プラットフォームとしては、Voicy と Stand.FM 等)から Clubhouse までその可能性と盛り上がりは高まるばかりです。
更には、先日ご案内のとおり 新作著書:コロナ禍での海外渡航術 発売になっています。
繰り返しになりましが、結構活発に活動しておりますので(笑)、引続きどうぞ宜しくご確認お願い致します。
ブログ・サイト リニューアルご連絡
こちらのHatenaBlogだけご覧になられている人は2020年9月以降こちらで更新がストップしているようにみえるかもしれませんが… 活動内容を以下のとおり変更・調整しておりました。
1.ブログサイトを別途リニューアル
2.日々の情報発信をブログから音声メディアに切替え
音声メディアについてはその可能性については別途解説させて頂きたいと思いますが、ポッドキャスト系メディア(私の活動プラットフォームとしては、Voicy と Stand.FM 等)から Clubhouse までその可能性と盛り上がりは高まるばかりです。
更には、先日ご案内のとおり 新作著書:コロナ禍での海外渡航術 発売になっています。
実は結構活発に活動しておりますので(笑)、引続きどうぞ宜しくご確認お願い致します。



